CIAを目指した理由
当社の監査部では、CIAの資格取得が強く推奨されています。個人の年間目標にもセットされますし、また、CIA(またはそれに準じる資格)がなければ、実質的に監査長を務めることができません。
自己研鑽の意味合いもありますが、まずは今いる組織でステップアップしたく、CIAの受験に臨んだ次第です。また、受験勉強を行う中で最新の監査実務・監査業界・環境変化等の知識を得られることも期待していました。海外子会社の監査部とコミュニケーションする機会も多く、そこで国際基準の知識をもっていれば共通の知識を土俵に話をできるだろうという狙いもありました。
アビタスを選んだ理由・メリット
CIAを受験するにあたりどのような勉強法が適切かを、すでに資格をお持ちの同僚の何人かに質問をしてみました。皆様一様に、予備校での受講により勉強を行ったようでした。そして同じく一様にアビタスを選択されていたため、自分も先輩諸氏の選択に乗ってみることにしました。アビタスに申し込む前にインターネットで受講形式や内容を確認したのですが、通信授業を選ぶことができる点・教科書が充実している点・質問窓口がある点などに好印象を受け、アビタスで受講することを決めました。
CIAの学習を通じて得た事、メリット等
CIAの勉強と並行して、監査チームに入り監査実務を担いました。そのため正直なところ、監査の流れや注意点については実務で学んだところが多いです。しかし受験勉強をすることで、IIA基準と自社の実務がどう違うか、という比較をすることができました。
自社の監査にはまだ改善点もありますし、将来に向かって変えていきたい部分もございます。そのあたりのポイントを知ることができたのは大変有効だったと考えます。加えてPart3の学習でこれまで知らなかった各業務領域の概要を学ぶことができました。特にIT領域の知識は有効で、今回の学習を起点としてIT関係の資格を取得しようと考えています。このように、他の資格へのステップとなる点は、私のみならず他の受験生様も同様に良い機会になるかと思います。
これからCIAを目指す方へのアドバイス等
自分の勉強法を記載しておきます。
まずは講義を一通り受講することです。特にPart3については不慣れでしたので、伊藤先生と八野先生の講義を両方受講しました。次に、MCカードを2周します。アビタスでは3周以上を推奨されていますが、3週目になると回答を覚えてしまっているため、無理に回数を増やす必要はないかと思います。回数よりも、一つ一つの問題について、正解、そして不正解の理由を充分に理解することが大事だと感じます。
私が工夫したのは、「書き込み」でした。受講中、教科書に感じたことを書き込んでいくのです。自分がわかりやすいように具体例を書き込んでもよいですし、自社の実務と照らし合わせた際の具体的な業務を書き込んでもよいです。疑問に思ったことや語呂合わせも含め、とにかく手を動かすことが肝要かと思います。なお、MCカードにも同様に書き込みました。耳と手を使って理解し、覚えていくわけです。
そしてこれは私のオリジナルですが、要点のみをwordに転記し、転記するという作業を経ながら覚えていきました。充分に理解していなければ、「要点を抜き出す」ことができないからです。
受験当日はルーティン(決まった時間帯に、決まったカフェでコーヒーを飲んでから行くなど)を行って頭を整え現地に臨みました。皆様のご成功を、心より願っております。
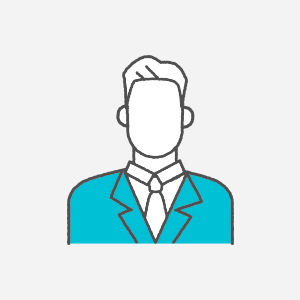
 CIA
CIA