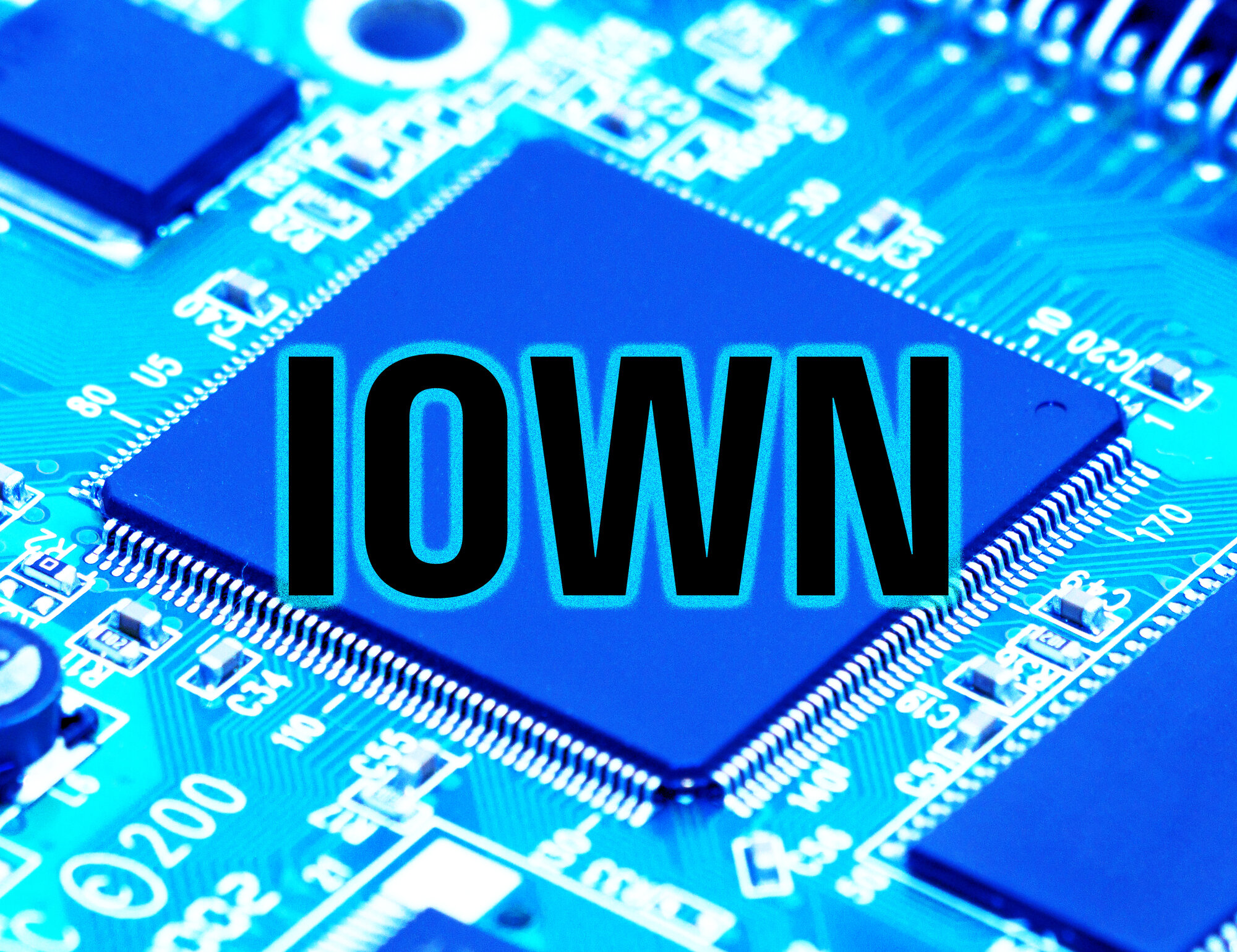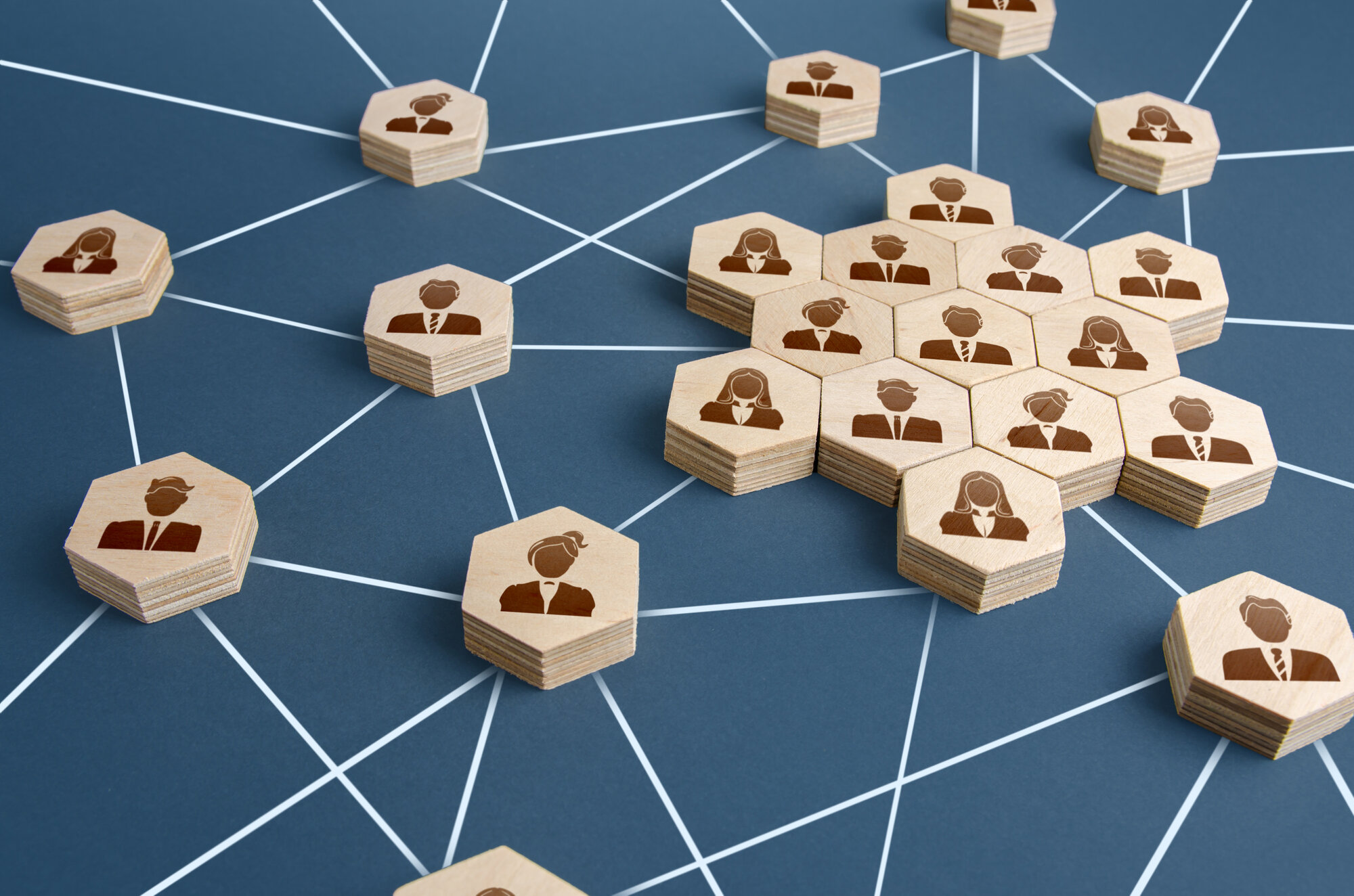本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。
- 2025/10/23公開
【第1回】なぜNTTは変わらなければならなかったのか?──独占から競争環境への転換と“規制の枷”──

【第1回】なぜNTTは変わらなければならなかったのか?
この記事を書いた人
目次
日本最大企業の「矛盾」
国営時代からの転換
競争環境の激変
NTTの“構造的課題”
なぜ「変わらなければならない」のか?
MBAの学びとの接点
日本最大企業の「矛盾」
日本電信電話株式会社(NTT)は、売上規模で日本最大級の企業グループであり、国内通信インフラの中枢を担う存在です。2023年度の連結売上は13.2兆円、従業員数は約33万人と、国の社会基盤を支える規模を誇ります。
一方でNTTには、他の民間企業にはない“矛盾”が横たわっています。「民営化された企業」でありながら、「国による規制下にある企業」という二重構造です。
国営時代からの転換
NTTの源流は1952年に設立された「日本電信電話公社」。国営体制の下、通信網の整備を進め、日本経済の高度成長を支えました。 1985年、民営化によって「NTT」として再出発しましたが、その時からすでに「規制の下での民営」という特殊な形態を背負っていました。
NTT法の制定(1984年)
公共性を重視し、国民に等しく通信サービスを提供する義務を課した。
株式の一部国保有
現在も政府が約33%を保有。完全な自由経営ではない。
市場独占の制約
地域会社(NTT東日本・西日本)の競争優位を制限する規制が課されている。
つまり、民営化は形式的であり、実質的には「規制の檻の中での経営」だったのです。
競争環境の激変
1990年代以降、通信市場は急速に競争環境に変わりました。
携帯電話の普及:1994年にNTTドコモが誕生。当初は圧倒的シェアを握ったが、KDDIやソフトバンクとの競争激化。
固定電話市場の衰退:携帯電話とインターネットの普及により、固定電話契約数は1998年の6,000万件から2022年には1,000万件以下へ激減。
光回線競争:フレッツ光を中心に全国展開するも、価格競争や新規参入に押され収益性は低下。
結果として、NTTは「かつての独占的地位」が競争環境の中で徐々に削がれていきました。
費用は留学の1/10
AACSB認証の高品質な米国MBAをオンラインで取得
まずは無料の説明会にご参加ください。
NTTの“構造的課題”
NTTが抱えてきた問題の本質は、単なる経営戦略の巧拙ではなく、「制度」と「組織構造」に深く根ざしたものでした。
規制と自由経営の狭間
電気通信事業法の下で、NTT東西は「ユニバーサルサービス義務」を負い、全国どこでも均一料金で通信を提供する責務があります。そのため料金設定や事業再編の自由度は小さく、競合であるKDDIやソフトバンクが柔軟に価格競争を仕掛けられる一方で、NTTは動きにくい状況に置かれてきました。例えば、光回線料金の大幅な値下げを自社判断だけで実施できないのは、その象徴的な制約です。
グループの肥大化と縦割り
持株会社のもとに、NTT東日本・西日本、NTTドコモ、NTTデータ、NTTコミュニケーションズなど多様な事業会社を抱え、グループ全体の従業員数は約33万人にのぼります。規模は世界最大級ですが、その一方で「縦割りの壁」が厚く、顧客へのサービスや海外事業での横連携がスムーズに進まないという課題を抱えています。たとえば、法人顧客が「通信+システム開発+クラウド」を一体で求めても、各事業会社の間で調整コストが発生し、意思決定が遅れるケースが指摘されてきました。
イノベーションの遅れ
NTTは年間約5,000億円という巨額の研究開発投資を続け、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)など世界最先端の技術構想を発表しています。しかし、規制や組織の硬直性が商用化を遅らせる要因となり、海外展開ではシリコンバレーや中国勢に比べて存在感が薄いのが現実です。基礎研究のレベルは高くても、「ビジネス化」「スピード感」という面で遅れを取っているのです。
これらの課題は、パナソニックやJALにも見られた「戦略よりも構造に根差した問題」であり、単なる戦略転換では解決が難しいという共通点があります。
なぜ「変わらなければならない」のか?
NTTが変革を迫られている理由は明白です。
・国内市場は成熟・縮小、通信料収入は右肩下がり。
・海外勢(GAFA、クラウドプレイヤー)が通信の上位レイヤーを支配。
・国家規制と市場競争という二重の圧力に挟まれている。
このままでは「国内インフラの守護者」で終わってしまうリスクがあります。だからこそ、グローバルなデジタル競争に耐えうる新しい事業構造を築く必要があるのです。
MBAの学びとの接点
NTTの事例は、MBAの学びに直結します。
| MBAの論点 | NTT事例の示唆 |
|---|---|
| 経営戦略論 | 独占から競争環境へ移行する際の競争優位の再定義 |
| コーポレート・ガバナンス | 国家規制と株主利益のバランスをどう取るか |
| 組織デザイン | 巨大グループをどう再編し全社最適を図るか |
| イノベーション論 | 研究開発投資を事業成果に結びつけるプロセス設計 |
単なる「通信会社」としてではなく、「規制に縛られた巨大企業の変革モデル」として読むと、NTTの存在は極めて示唆的です。
次回予告
第2回では、1999年の持株会社化と2020年のドコモ完全子会社化を軸に、NTTがどのように組織を再設計してきたかを分析します。
「分割」と「統合」の二つの動きから、ガバナンスと戦略のダイナミクスを読み解いていきます。
次の記事はこちら
費用は留学の1/10
AACSB認証の高品質な米国MBAをオンラインで取得
まずは無料の説明会にご参加ください。
アビタスでは、国際認証を取得している「マサチューセッツ州立大学(UMass)MBAプログラム」を提供
国際資格の専門校であるアビタス(東京)が提供しているプログラムで、日本の自宅からオンラインで米国MBA学位を取得できます。
日本語で実施する基礎課程と英語で行うディスカッション主体の上級課程の2段階でカリキュラムが組まれているため、英語力の向上も見込めます。
世界でわずか5%のビジネススクールにしか与えられていないAACSB国際認証を受けており、高い教育品質が保証されているプログラムです。
自宅にいながら学位が取得できるため、仕事や家事と両立できる点も強みです。
アビタスでは無料のオンライン説明会と体験講義を実施しています。興味のある人はお気軽にお問い合わせください。
 UMass MBA
UMass MBA