本ウェブサイトでは、Cookieを利用しています。本ウェブサイトを継続してご利用いただく際には、当社のCookieの利用方針に同意いただいたものとみなします。
- 2025/04/30公開
IFRS(国際会計基準)を導入するメリット・デメリット、注意点を解説
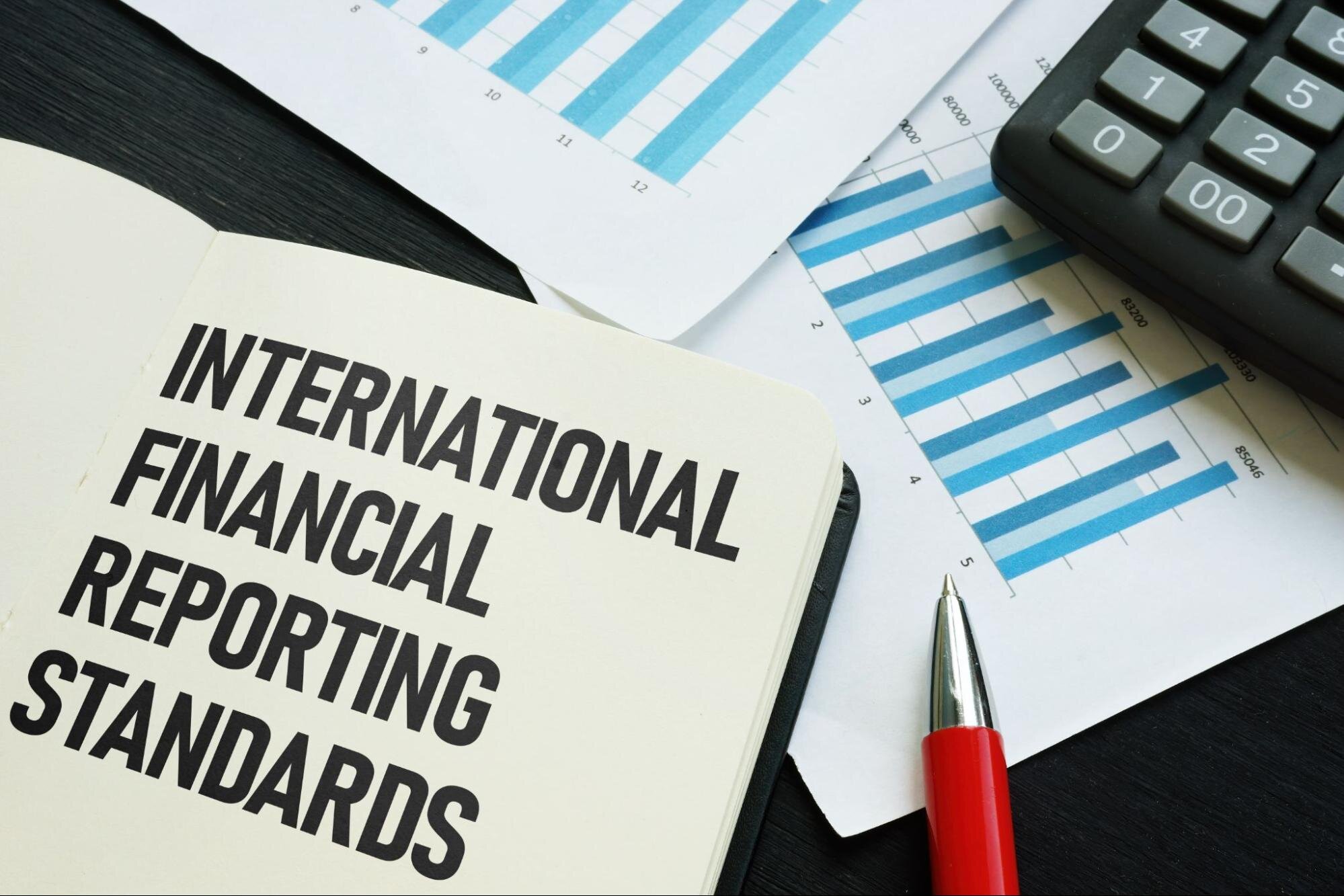
IFRS(国際会計基準)は、グローバルな事業展開を行っている企業にとってさまざまな点でメリットがある会計基準です。しかし、その特徴やメリットについてしっかりと理解できていないという人も少なくはありません。
本記事では、IFRS(国際会計基準)の概要や導入するメリット・デメリット、導入における注意点などを解説します。
目次
IFRS(国際会計基準)とは
IFRS(国際会計基準)導入の5つのメリット
IFRS(国際会計基準)導入の3つのデメリット
IFRS(国際会計基準)について認識すべき3つの注意点
IFRS(国際会計基準)導入はメリット・デメリットを踏まえて検討しよう
IFRS(国際会計基準)とは
IFRS(国際会計基準)とは、国際会計基準審議会(IASB)が世界共通の会計基準とすることを目標として定めた会計基準のことです。
これまで、各国では独自の会計基準が採用されていましたが、グローバル化を図る企業にとって進出先の国の決算書類と比較することが難しいという実態がありました。このように企業のグローバル展開が進んでいったことから世界共通で使える会計基準が必要となり、IFRS(国際会計基準)が定められたという経緯があります。
IFRS(国際会計基準)は世界的にも広く普及しており、日本でも2010年3月期の決算から上場企業の連結財務諸表において任意適用が認められています。
関連ページ:アビタス IFRS「IFRSとは」
IFRS(国際会計基準)導入の5つのメリット
IFRS(国際会計基準)を導入することは、特にグローバルに事業を展開する企業にとって多くのメリットがあります。具体的には、以下の5つが挙げられます。
- 財務情報を海外拠点とも統合できる
- 海外投資家からの資金調達を得やすくなる
- 海外の競合他社と比較しやすい
- 財務情報や業績を正確に把握しやすい
- M&A時、のれん代の償却が不要
上記の5点について、1つずつ詳しく解説します。
財務情報を海外拠点とも統合できる
IFRS(国際会計基準)を導入することで、海外に拠点のある企業では、異なる会計基準で作成された財務情報を統一の基準で把握し、連結財務諸表の作成を効率的に行うことが可能になります。
日本国内に本社を持ち海外支店などを有している企業の場合でも、IFRS(国際会計基準)の導入によって同一の会計基準を使用するため、財務情報の統合化につながります。
海外拠点の財務状況をグループ全体として一元的に管理できると、経営判断の迅速化やリスク管理の強化が図れます。また、グローバルな視点からの経営戦略の立案にも役立ちます。
海外投資家からの資金調達を得やすくなる
IFRS(国際会計基準)を導入することで、財務諸表が国際的に比較できるようになり、海外投資家からの信頼を得やすくなるでしょう。その結果として、海外からの資金調達が円滑に進むことが期待できます。
海外投資家から見ると、日本の会計基準に則って作成された財務諸表は把握しにくい面があります。しかし、IFRS(国際会計基準)の導入により、海外投資家が財務内容を理解しやすくなれば、海外投資家からの資金調達につながる可能性があります。
このように、グローバル化を目指す企業にとっては、資金調達の観点からもIFRS(国際会計基準)は重要な役割を果たします。
海外の競合他社と比較しやすい
海外の競合他社と採用している会計基準が異なると、日本の会計基準に則した財務諸表と比較することは難しいでしょう。
IFRS(国際会計基準)の導入によって、海外の競合他社との財務情報の比較が容易となれば、事業戦略の策定や競争力の分析にも役立ちます。
財務情報や業績を正確に把握しやすい
IFRS(国際会計基準)では、日本会計基準と比較して可視化できない状況の把握が可能となります。具体的な状況としては以下のとおりです。
- 収益の認識方法や財務諸表への計上タイミング
- 有給休暇引当金 ※1
- のれん代 ※2
※1 従業員が未取得の有給休暇の金額を、将来の支払いに備え決算時に負債計上したもの
※2 企業買収の際に支払われる買収金額と売り手企業の純資産額との差額
これらの状況把握が可能になることで、財務情報や業績などをより正確に把握しやすくなるでしょう。
また、IFRS(国際会計基準)では貸借対照表が重視されており、長期的な企業の価値についても測りやすいといわれています。
M&A時、のれん代の償却が不要
IFRS(国際会計基準)では、のれんは非償却となっており、会計上の利益が減りにくいという特徴があります。
日本会計基準では、M&Aにより生じたのれん代は20期以内に毎期規則的に償却することが定められていますが、IFRS(国際会計基準)では定期的な償却は行われません。少なくとも年に一度の減損テストを行うことが求められており、価値の減少が認められた場合に、減損損失を計上します。
IFRS(国際会計基準)のこの減損計上モデルは、投資家が経営者の買収戦略が企業価値の向上に寄与しているかの評価を可能にし、今後の投資判断に役立ちます。
関連記事:アビタス IFRS「のれんの償却におけるIFRSと日本基準の差異」
まずは無料の説明会にご参加ください。
IFRS(国際会計基準)導入の3つのデメリット
IFRS(国際会計基準)導入にはメリットだけでなく、次のようなデメリットも考えられます。
- 導入コストがかかる
- 業務負担が増える
- 財務報告の変換(コンバージョン)が必要
導入を検討するにあたり、これらの点もしっかり理解しておく必要があります。1つずつ詳しく見ていきましょう。
導入コストがかかる
IFRS(国際会計基準)へ移行する場合、多岐にわたり導入コストが発生します。主なコストは以下のとおりです。
- 調査・分析に要するコスト
- 会計システムの導入や変更、更新費用
- 外部コンサルタント・アドバイザーなどの専門家に支払う費用
- 経理担当者の教育費用
これらのコストと企業規模の間には正の相関関係があり、規模が拡大するとコストも増大する傾向があります。場合によっては移行に数年単位の期間を要するため、初期費用だけでなく、長期的な運用コストも含めた総合的な費用を検討する必要があることも覚えておきましょう。
業務負担が増える
IFRS(国際会計基準)へ移行を進めると、これまでとは異なる業務プロセスを踏む必要があることから、業務負担が増える傾向があります。
IFRS(国際会計基準)は会計原則に重要性を持たせていることから、詳細な規則が定められていません。そのため、財務諸表を作成する際には、経営者の判断とその根拠を明確に示さなければなりません。より詳細な注記を行うために、会計担当者の負担が増加する可能性があります。
また、新システムに慣れることや、事務処理の負担増加に対応できるような組織の仕組みづくりも重要です。内部統制の強化や業務効率化を図るためのマニュアルの作成や見直しも求められるでしょう。
さらに、IFRS(国際会計基準)に基づく財務諸表は英語で作成するため、専門的な会計知識に加え、高い英語能力を有する人材の確保が不可欠です。
財務報告の変換(コンバージョン)が必要
IFRS(国際会計基準)で財務諸表を作成する場合、財務報告の変換(コンバージョン)が必要です。
IFRS(国際会計基準)を適用している企業では、グループ全体の連結財務諸表はIFRS(国際会計基準)で作成しますが、個々の企業の財務諸表は日本会計基準に基づいて作成しなければなりません。
日本会計基準で作成した個別財務諸表を連結する際に、IFRS(国際会計基準)に合わせて変換する必要があり、別途の作業や手間がかかります。
IFRS(国際会計基準)について認識すべき3つの注意点
IFRS(国際会計基準)の導入においては、以下の3つの注意点についても認識しておくとよいでしょう。
- 会計方針の変更が必要
- 資産評価の基準が異なる
- 「初度適用」を行わなければならない
計画的かつ円滑に導入を進められるよう、各注意点について理解しておきましょう。
会計方針の変更が必要
IFRS(国際会計基準)を導入すると、現在の会計基準と異なる「リース会計基準」や「固定資産の会計方針」への変更が必要です。
リース取引について、日本会計基準ではオペレーティングリースはオフバランス処理となっていますが、IFRS(国際会計基準)ではオンバランス処理が求められています。 なお、日本でも2027年4月以降の会見年度から、IFRS(国際会計基準)を踏まえた「新リース基準」が大企業などに強制適用となっています。
「固定資産会計」については、耐用年数の見積もり方や取得原価に含まれる範囲、減損の戻入など、固定資産の減損に関する取り扱いが異なります。
こうした変更に際し、担当者の教育やシステム変更など、時間的・金銭的なコストが増加することを理解しておくことも大切です。
参照:ASBJ(企業会計基準委員会)「リースに関する会計基準」
資産評価の基準が異なる
IFRS(国際会計基準)では「資産・負債アプローチ」が採用されており、計上する時点の「時価」を重視する「公正価値評価」が資産評価の基準となっています。また、非上場株式も時価評価を適用することとされています。
一方、日本会計基準では「取得原価主義」が採用されており、資産評価の基準は取得時の価格(簿価)を原価として評価するのが一般的です。
このように資産評価の基準が異なるため、IFRS(国際会計基準)への移行の際には十分な注意が必要です。
「初度適用」を行わなければならない
IFRS(国際会計基準)を初めて適用した年度においては、「初度適用」を行うことが求められます。
初度適用とは、初めてIFRS(国際会計基準)を適用した財務諸表を作成することです。前期と当期を合わせた少なくとも2期分の財務情報を開示する必要があり、具体的には、以下の書類の作成を行います。
- 財務状態計算書(3期分)
- 包括利益計算書(2期分)
- 株主持分計算書(2期分)
- キャッシュ・フロー計算書(2期分)
- 注記
通常よりも作成にかかる量が多く時間もかかるため、業務負担の増加に注意しましょう。
IFRS(国際会計基準)導入はメリット・デメリットを踏まえて検討しよう
IFRS(国際会計基準)の導入企業は各国で増加傾向にあります。日本では現在、任意導入となっていますが、今後グローバルな展開を進めていく企業を中心に増加していくことが予想されます。
IFRS(国際会計基準)の導入には、グローバル化を目指す企業にとってさまざまなメリットがある一方で、業務量やコストの増加、専門的な知識のある担当者の確保など、デメリットや注意点などもあります。
これらを十分に理解し、自社にとって有効なものかどうかを検討しましょう。
IFRS検定試験の合格を目指すならアビタス
IFRS検定試験の合格を目指すならアビタスを検討してみましょう。
アビタスのIFRS Certificateプログラムは2008年の開講以来、多くの合格者を輩出し続けています。最新の試験傾向を踏まえた重要項目を分かりやすく解説したオリジナル教材を提供しており、日本会計基準との差異も理解できるため実務にも役立ちます。
効率よく学習できるよう、充実した学習ツールを準備しており、最短3カ月での合格が可能です。
アビタスではオンラインによる無料説明会を実施しています。興味のある方はお気軽にご参加ください。
 IFRS
IFRS






